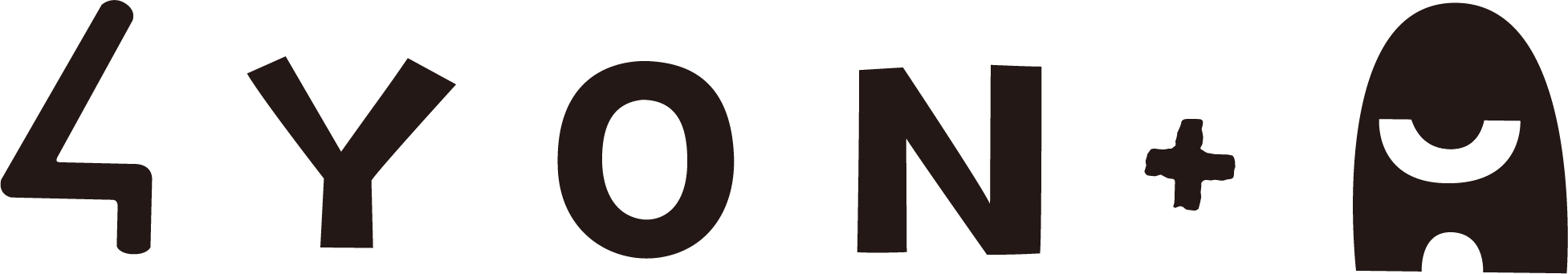オリジナルキャラクターの制作方法は?依頼先の選び方を徹底解説
オリジナルキャラクターを作って自社のブランディングを強化したいけれど、何から始めれば良いのか迷っていませんか?
デザインの流れや依頼先の選び方、制作にかかる費用の相場、さらにキャラクターの著作権はどう扱えばいいのかなど、不安や疑問は多いものです。
本記事では、そうした悩みを解消するためにオリジナルキャラクター制作の基本知識から具体的な制作方法、プロへの依頼方法、自作との違い、そして著作権のポイントまでを徹底解説します。
初心者の方でも分かりやすいように、失敗しないためのポイントも交えてご紹介しますので、読めばきっと「キャラクター制作を始めてみよう」と一歩踏み出す自信が持てるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
オリジナルキャラクターとは?
オリジナルキャラクターとは、企業や個人が自社・自身のイメージに合わせて新たに作り出した独自のキャラクターのこと。ロゴマークでは表現しきれない親しみやすさを持つキャラクターが、企業や個人の象徴(顔)として活躍します。まずは、その制作の目的と活用シーンを見てみましょう。
キャラクター制作の目的と活用シーン
企業がオリジナルキャラクターを制作する主な目的は、ブランディングの強化です。親しみやすいキャラクターを通じて社名やサービス名を覚えてもらいやすくし、他社との差別化を図る狙いがあります。
また、個人のクリエイターにとっては、自身の分身となるキャラを作ることでファンとのコミュニケーションを円滑にしたり、活動の幅を広げたりする目的もあるでしょう。
こうしたキャラクターは様々なシーンで活用されています。例えば、企業ならWebサイトやパンフレット、製品パッケージに登場させてブランドをアピールできます。SNSやブログのアイコン、投稿コンテンツにキャラを登場させれば、フォロワーに親近感を与えやすくなります。
イベントや展示会で着ぐるみ(マスコット着用スタッフ)として来場者を出迎えたり、ノベルティグッズやLINEスタンプにして配布・販売したりと、活用方法は無限大です。
企業・個人がオリジナルキャラを使うメリット
オリジナルキャラクターを導入するメリットも多岐にわたります。まず、視覚的なインパクトと可愛らしさでキャラクター自体のファンが生まれ、「◯◯というキャラ=◯◯会社」や「◯◯さんのキャラ」と自然に認知してもらえる効果があります。結果としてブランド認知度や好感度が向上し、商品やサービスのPR効果が高まります。
さらに、一度キャラクターを作ればSNSやオウンドメディアで繰り返し活用でき、広告費をかけずに継続的な発信が可能になります。キャラクターが話題になれば関連グッズの販売といった収益化のチャンスも生まれますし、他企業や自治体とのコラボレーションに発展するケースもあります。
また、キャラクターの設定や口調を定めておけば、複数人でSNS運用する際も一貫した世界観を保ちやすいといった利点もあります。企業だけでなく、個人にとっても活動のシンボルができることでモチベーションが上がり、ファンとの絆を深める効果が期待できます。
オリジナルキャラクター制作の流れ

オリジナルキャラクターを作る際は、いきなり可愛いイラストを描き始めるのではなく、まずしっかりと準備と設計を行うことをおすすめします。一般的な制作プロセスを、以下の3ステップに沿って見てみましょう。
1. キャラクターのコンセプト設計
まず初めに、キャラクターのコンセプト(基本設定)を固めます。これはキャラクターの「テーマ」や「役割」を決める作業です。例えば、キャラクターの対象年齢や性格、口調、そしてブランドとの関係性を考えます。
企業のマスコットなら、会社の商品やサービスの特徴を盛り込んだ設定にすると良いでしょう。個人のキャラクターであれば、自分自身の分身としてどんな性格やストーリーを持たせたいかを自由に発想します。この段階でキャラクターの名前や簡単な背景ストーリーを考えておくと、デザインがぶれにくくなります。
2. デザイン案のラフ制作
コンセプトが決まったら、次は実際にビジュアルのアイデア出し(ラフスケッチ)を行います。いきなり完璧を目指す必要はありません。まず紙と鉛筆やデジタルツールで思いつくままに絵を描いてみましょう。複数のデザイン案をラフで用意して、どのイメージがコンセプトに最も合致するか比べます。
たとえば、キャラクターの形状(人型か動物か、など)や表情、服装のパターンなど、いくつかバリエーションを描いて検討します。制作会社やプロに依頼する場合でも、初期段階ではラフイラストを複数提案してもらい、その中から方向性を決めていくのが一般的です。このラフ制作段階では細かいクオリティよりもアイデアの幅を重視し、自由に発想することがポイントです。
3. 清書・デジタル化と納品データの種類
ラフデザインの中から採用する案が決まったら、いよいよキャラクターを清書して仕上げます。線画を綺麗に描き直し、カラーリングや細部のディテールを作り込んでいきます。最近は最初からペンタブレットを使ってデジタル化するケースが多いですが、手描きのラフをスキャンしてパソコン上でペン入れ・着色する方法でも構いません。
完成したイラストは、用途に応じたデータ形式で保存・納品します。印刷物や拡大縮小を考慮するならベクター形式であるAdobe Illustratorの.aiデータやPDF形式が望ましいです。WebサイトやSNSで使うなら背景が透明なPNG画像が便利でしょう。
また、キャラクターをアニメーション化したりグッズ展開したりする予定がある場合は、パーツ分けしたPSDデータを用意しておくと後の加工がしやすくなります。納品時にはカラープロファイルの指定や解像度(dpi)の確認も忘れずに行い、必要に応じて複数のサイズ・形式で書き出しておくと安心です。
キャラクターを自作する方法

オリジナルキャラクターの制作方法には、大きく分けて「自作」と「外注」があります。まずは、自分でキャラクターを作りたい場合の方法を見てみましょう。絵を描くスキルに自信がある方はもちろん、初心者でも使いやすいツールが増えており、工夫次第で魅力的なキャラクターを自作できます。
初心者におすすめのデザインツール
デジタルイラストに慣れていない初心者でも扱いやすいお絵描きツールが多数存在します。まず、スマホやタブレットで気軽に描きたいならアイビスペイント(ibisPaint)やメディバンペイント(MediBang Paint)など無料アプリがおすすめ。指先やタッチペンで直感的に操作でき、レイヤー機能やペンブラシも充実しています。
パソコンで本格的に描く場合は、無料ソフトのFireAlpaca(ファイアアルパカ)などから始めてみると良いでしょう。有料でもプロも愛用するCLIP STUDIO PAINT(クリスタ)や Adobe Photoshopなどは表現力が高く、さらにAdobe Illustratorを使えば拡大・縮小しても画質が劣化しないベクターイラストとして綺麗な線画を描けます。
まずは手に取りやすいツールで練習し、慣れてきたら必要に応じて高度なソフトにステップアップすると良いでしょう。なお、紙に鉛筆で描いたイラストをスキャンしてデジタル化するという手もあります。ツールにこだわりすぎず、自由な発想で何度も描いてみることが自作上達のコツです。
イラストを描けない人向けの AI ツール活用法
「絵心がないけどオリジナルキャラが欲しい」という方には、AIイラスト生成ツールの活用が画期的な手段となります。近年登場したAI 画像生成サービス(例:MidjourneyやStable Diffusion系のツール)は、テキストで「こういうキャラクターが欲しい」と指示するだけで、それに沿ったイラストを自動で描いてくれます。例えば「優しい表情の猫のマスコットキャラクター」「和風テイストのゆるキャラ」といった具合に日本語で特徴を入力すれば、数十秒で候補画像が生成されます。絵が描けなくても理想のビジュアルを形にできるのが大きな魅力です。
ただし、AIツールを使う際はいくつか注意点もあります。まず、思い通りのキャラを得るにはプロンプト(入力文)の工夫が必要で、何度も生成と調整を繰り返す手間はかかります。
また、一度に複数のポーズや表情差分を作るのはAIでは難しく、キャラクターの一貫性を保った画像を揃えるのは苦手です。そのため、最終的な仕上がりを整えるために AI で出力した画像を元に加筆修正したり、プロの手でクオリティを高めてもらったりするケースもあります。
さらに、AIが生成した画像の著作権や商用利用には注意が必要です。サービスによって利用規約が異なり、無料版では商用利用不可の場合や、生成物に著作権が発生しない(誰でも使える)場合もあります。
安心して使うためにも、利用している AIサービスの規約を確認し、必要に応じて有料版の契約やクレジット表記などの条件を守りましょう。また、AIでたまたま既存キャラクターに似たデザインが出てしまう可能性もゼロではありません。公開前にオリジナリティを確認し、トラブルを避ける配慮も大切です。
プロに依頼して制作する方法

「自分で描くのは難しい」「クオリティの高いキャラを作りたい」という場合は、プロのイラストレーターやデザイン会社に外注する方法があります。ここでは、依頼先の種類や費用相場、そして実際に依頼する際に準備すべきことを解説します。
依頼先の選び方。個人?制作会社?クラウドソーシング?

キャラクター制作をプロに依頼する場合、主に次のような選択肢があります。それぞれメリット・デメリットが異なるため、自身のニーズに合った方法を選びましょう。
フリーのイラストレーター(個人)に依頼
好みの作風のイラストレーター個人に直接依頼する方法です。XやPixivで見つけたクリエイターにDMを送ったり、イラストコミッションサイト(例: SKIMAやココナラなど)を利用したりして依頼できます。仲介がない分料金を抑えられます。ただし人気クリエイターは多忙で納期が延びることもあり、ビジネス上のやり取りに不慣れだと打ち合わせに時間がかかる場合もあります。
デザイン制作会社に依頼
キャラクターデザインの実績が豊富な制作会社に依頼する方法です。企業向けに多くのキャラクター開発を手掛けている会社なら、打ち合わせ(ヒアリング)から納品まで安心して任せられます。ディレクターを含むチーム体制でクオリティも安定し、自社の要望に沿ったキャラを制作してもらえます。ただし費用は個人より高め(場合によっては数倍)になる点には注意しましょう。
クラウドソーシングサービスを活用
オンライン上でクリエイターに仕事を募集・発注できるクラウドソーシングサイトを使う方法です。国内では「クラウドワークス」や「ランサーズ」といったサービスに多くのフリーランスデザイナーが登録しています。予算を決めコンペ形式で募集すれば、多数の案から選べる利点があります。ただ、応募作品のクオリティには幅があるため、最適案の選定やその後の交渉に手間がかかることも。利用の際は実績や評価を確認し、信頼できるクリエイターを選ぶことが大切です。
料金相場と費用の決まり方

気になる費用相場ですが、キャラクターデザインの料金は依頼する相手や条件によって大きく変動します。大まかな目安として、個人のフリーイラストレーターに一体のキャラデザインを頼む場合は数万円程度から、実績や知名度のあるプロや制作会社に依頼する場合は十万円以上を見込んでおくと良いでしょう。
例えば、簡易な立ち絵1枚のみなら数万円、ポーズ違いや表情差分まで含めると20万円以上になるケースもあります。もちろん案件によってはそれ以上の予算になることもありますし、逆に学生クリエイターなどに依頼して数万円以下で済むケースもあります。
費用を左右する主な要素として、キャラクターの難易度(シンプルか描き込みが多いか)、納品物の内容(立ち絵1枚のみか、差分・複数ポーズありか)、商用利用や著作権譲渡の有無、クリエイターの経験値、修正回数、納期の緊急度などが挙げられます。
なお、完成後に著作権ごと譲渡してもらう場合は、通常の使用許諾より料金が割増になるのが一般的です。依頼前に複数の候補から見積もりを取り、料金内訳や対応範囲(何案提案してもらえるか、修正は何回まで含むか等)を比較検討すると安心です。
依頼時に必要な準備・伝えるべきこと
プロにキャラクター制作を依頼する際は、こちらから要望を的確に伝えることが成功のポイントです。スムーズなやり取りのために、事前に次のような事項を整理しておきましょう。
キャラクターのコンセプトやイメージ
どんな設定や性格のキャラクターにしたいのか言語化して伝えます。ターゲット層も共有すると方向性を掴みやすくなります。可能であれば、好きなテイストの参考画像や既存キャラクターの例を数点用意し、「この部分を参考にしてほしい」「こういう雰囲気は避けたい」など具体的に伝えると良いでしょう。また、デザイン上で取り入れたい要素や避けたい要素があれば、この段階で共有しておきます。
利用用途と納品ファイル形式
キャラクター完成後にどのように使用する予定かも重要です。Webサイトや印刷物、LINEスタンプ展開、グッズ化など具体的な用途によって、適したファイル形式や描き込み具合が異なります。例えば、グッズ化するなら高解像度データやAdobe Illustrator形式のベクターデータが望ましく、アイコン用途なら小さめのPNGで十分です。用途に応じた納品データの希望(ファイル形式やサイズ、カラーモードなど)があればあらかじめ伝えておきます。
予算・納期・権利関係の希望
あらかじめ予算の上限や希望納期がある場合は正直に伝えましょう。また、著作権の扱いについて、完成後に権利を譲渡してもらいたいのか、制作実績として公開は控えてほしいか、といった希望があれば契約前に確認しておく必要があります。特に商用利用の範囲やグッズ販売の有無などは重要なポイントですので、口頭だけでなく契約書や発注書の形で明文化しておくと安心です。
著作権・商用利用の注意点

オリジナルキャラクターのデザインが完成したら、それで安心…とはいきません。知的財産権に関する取り決めも重要なステップです。権利処理をおろそかにすると、後々思わぬトラブルに発展する可能性があります。ここでは著作権の基本知識と、商用利用時に注意すべきポイントを確認しましょう。
著作権の基本と「譲渡」or「利用許諾」の違い
キャラクターのイラストにも当然ながら著作権が発生します。日本の著作権法では、原則として「作品を実際に描いた人(創作者)」がその著作権を持ちます。つまり、自社内で社員が制作した場合は会社に帰属させられますが、外部のクリエイターに依頼して作ってもらった場合、何も取り決めをしないと基本的には描いた本人(クリエイター)に権利が残るのです。
このため第三者に依頼して制作したオリジナルキャラクターについて自社で自由に活用したり保護したりするには、契約で著作権の扱いを明確に決めておく必要があります。契約上の選択肢としては、大きく「著作権を譲渡してもらう」か「著作物の利用許諾(ライセンス)を受ける」かの二通りがあります。
著作権譲渡
キャラクターの著作権自体を制作者から買い取る契約です。譲渡すれば以降の権利者は依頼主となり、制作者は著作権を主張できなくなります(※著作者人格権は譲渡不可だが「行使しない」旨契約可能)。
利用許諾(ライセンス)
著作権は制作者に残し、利用する権利だけ得る契約です(こちらの方式が一般的)。契約書で使用できる範囲(媒体・期間・地域・改変可否など)を取り決めます。制作者は著作権者として存続するため、自身の作品公開などは可能です。自社専用にしたい場合は独占的な許諾にするか、著作権ごと譲り受ける方が安全でしょう。
著作権の取り扱いによって費用も変わる点にも注意しましょう。譲渡してもらう場合はライセンス許諾より高額になる傾向があります。しかし将来的にキャラクターを広く展開したり、第三者による無断利用を法的に止めたりしたい場合には、譲渡を受けて自社の財産としておく方が安心です。
トラブルを防ぐための契約・確認ポイント

最後にキャラクター制作にまつわる契約上の注意点を押さえておきましょう。以下のポイントを事前に確認・契約しておくことで、「こんなはずじゃなかった」というトラブルを防げます。
権利範囲を明記する
著作権を譲渡するのか、利用許諾のみかを契約書に明記します。特に利用許諾の場合は、利用できる範囲(媒体、期間、地域、改変の可否など)を細かく定めておきましょう。依頼主が求める用途を将来の展開まで見据えて網羅し、制作者側にも「制作実績として公開して良いか」「他への二次利用は禁止」など残る権利を取り決めておきます。
デザインのオリジナリティ保証
契約時に制作者から「第三者の権利を侵害しないオリジナル作品」であることを保証してもらいましょう。他社キャラの模倣でないか依頼主側でもチェックし、問題があれば修正を求めます。
契約書の締結
契約書を必ず交わしましょう。料金・納期・納品物・権利関係・秘密保持などを明記します。(口頭だけでなくメール等で必ず証跡を残してください)
商用利用の範囲確認
キャラクターをどこまで商用利用できるか契約で定めます。キャラクターグッズを製造・販売して利益を得ることまで許諾範囲かどうか、事前に合意しておけば「こんな用途は聞いてない」というトラブルを防げます。
以上の点をしっかり確認し、適切に契約処理しておけば、オリジナルキャラクターの運用で大きなトラブルに見舞われるリスクは格段に減るでしょう。大切な自社キャラクターを安心して活用できるよう、権利面の手続きも抜かりなく行ってください。
成功するキャラクターの共通点とは

キャラクターが完成したら、次はそれをどう活かすかが重要です。せっかく生み出したキャラクターですから、多くの人に愛され、長く活躍してほしいですよね。ここでは、人気キャラクターに共通する要素と、制作後にキャラクターを効果的に運用するアイデアをご紹介します。
人気キャラクターに共通する3つの要素
まず人気キャラクターに共通する要素を3つご紹介します。
1. 親しみやすく愛されるキャラクター性
幅広い層から「かわいい」「面白い」と感じてもらえる親しみやすさと、他にないユニークさを兼ね備えている。
2. シンプルで記憶に残りやすいデザイン
色数や要素を絞り、一目で特徴がわかるシルエットや表情を持つため覚えやすい。
3. 明確なコンセプトとストーリー
背景設定や性格付けがしっかりしており、キャラクターの世界観が明確でブランドメッセージとも一貫している。
制作後の運用アイデア
キャラクターは作って終わりではなく、その後の育て方が肝心です。以下のような活用アイデアを参考に、あなたのキャラクターをぜひ様々な場面で活躍させてみてください。
SNSの「中の人」として活躍させる
キャラクターが自社公式SNSアカウント上で発言したり、情報を発信したりする演出です。ユーザーとのやり取りもキャラの口調で行えば、親近感が湧きファンとの距離が縮まります。。
LINEスタンプを作成する
キャラクターの LINE スタンプを制作して公開すれば、顧客やファンが日常的にそのキャラを使ってくれるようになります。認知拡大や話題作りに効果的です。
グッズ展開やノベルティ配布
キャラクターをデザインしたグッズ(ステッカー、キーホルダー、Tシャツなど)を作って販売・配布します。イベントや展示会で配ると宣伝になりますし、社内で配布して社員のモチベーションアップにつなげるケースもあります。
動画やアニメーションで登場させる
キャラクターが動いて喋る動画コンテンツを制作するのもおすすめです。SNS広告用のショートアニメや、 YouTube の企業紹介動画にマスコットとして出演させると注目度が上がります。
オリジナルキャラクターでブランディングを強化しよう
オリジナルキャラクター制作の基礎知識から活用方法まで、一通りご紹介しました。自社や自身の魅力を体現するキャラクターがいれば、ブランド発信の心強い味方になってくれるでしょう。中小企業や個人事業主にとっても、キャラクターは決して大企業だけのものではありません。今回の解説をヒントに、ぜひキャラクター制作にチャレンジしてみてください。
とはいえ、「やっぱり自分で考えるのは難しい」という場合は、プロの力を借りるのも有効です。制作会社 4YON でもオリジナルキャラクター制作を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。あなたのブランドにぴったりのキャラクターを一緒に生み出しましょう!
4 YONではオリジナルキャラクターを一から丁寧に制作するサービスを提供しています。デザインから設定構築までを一貫して行い、ご依頼者さまの想いや世界観を大切に反映します。ビジュアルだけでなく、性格や背景ストーリーまで細やかに対応し、配信活動・SNS・グッズ展開など多様な用途に適したキャラクターをご提案します。ヒアリングを重ねながら、理想のかたちを一緒に作り上げていきます。創作初心者の方でも安心してご相談いただけるよう、丁寧なサポートを心がけています。キャラクターを通じて、あなたの想いを形にしてみませんか?
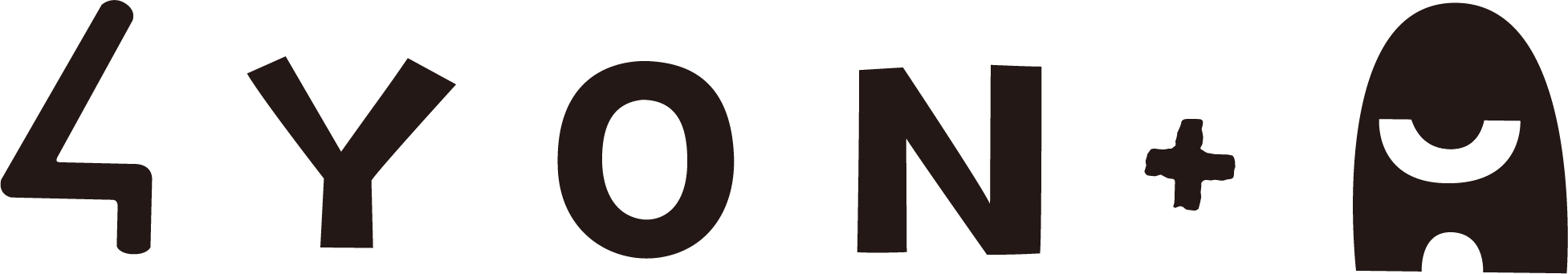
| 4 YON | |
|---|---|
| 住所 | 〒989-3212宮城県仙台市青葉区芋沢字赤坂32-62 |
| 電話 | 0223-95-4996 |
よくある質問
Q. 無料のキャラ作成アプリと有料ソフトの違いは何ですか?
A. 無料で使えるキャラクター作成アプリは直感的な操作と多彩なパーツ選択が魅力で、初心者でも数分でアイコン用イラストが完成する手軽さがあります。しかし、保存形式がPNG限定だったり、商用利用が不可な場合も多く、オリジナリティやライセンス面で制限がある点には注意が必要です。一方、有料ソフトやプロ依頼では、描き下ろしによる高い独自性、パーツの細分化、AI生成とのハイブリッド対応、Live2Dやアニメーション用のモデリングなど、より自由なキャラクターデザインが可能になります。無料ツールは用途が限定されやすいため、用途や目的に応じて使い分けることが重要です。
Q. 商用利用できるオリジナルキャラクターイラストはどのように見極めるべきですか?
A. 商用利用可否の見極めで最も大切なのは、使用するイラストやアプリの「利用規約」を細部まで確認することです。安心して使うには、商用利用が明記されている、または著作権譲渡の契約が可能なクリエイターへの直接依頼がベストです。特に企業ロゴ、グッズ展開、プロモーション素材に使う場合は、形式、カラーコード、セット納品、納品形式(PSDやAIファイルなど)も含めた仕様をクリアにすることで、後々のトラブル回避に繋がります。
会社概要
会社名・・・4 YON
所在地・・・〒989-3212 宮城県仙台市青葉区芋沢字赤坂32-62
電話番号・・・0223-95-4996